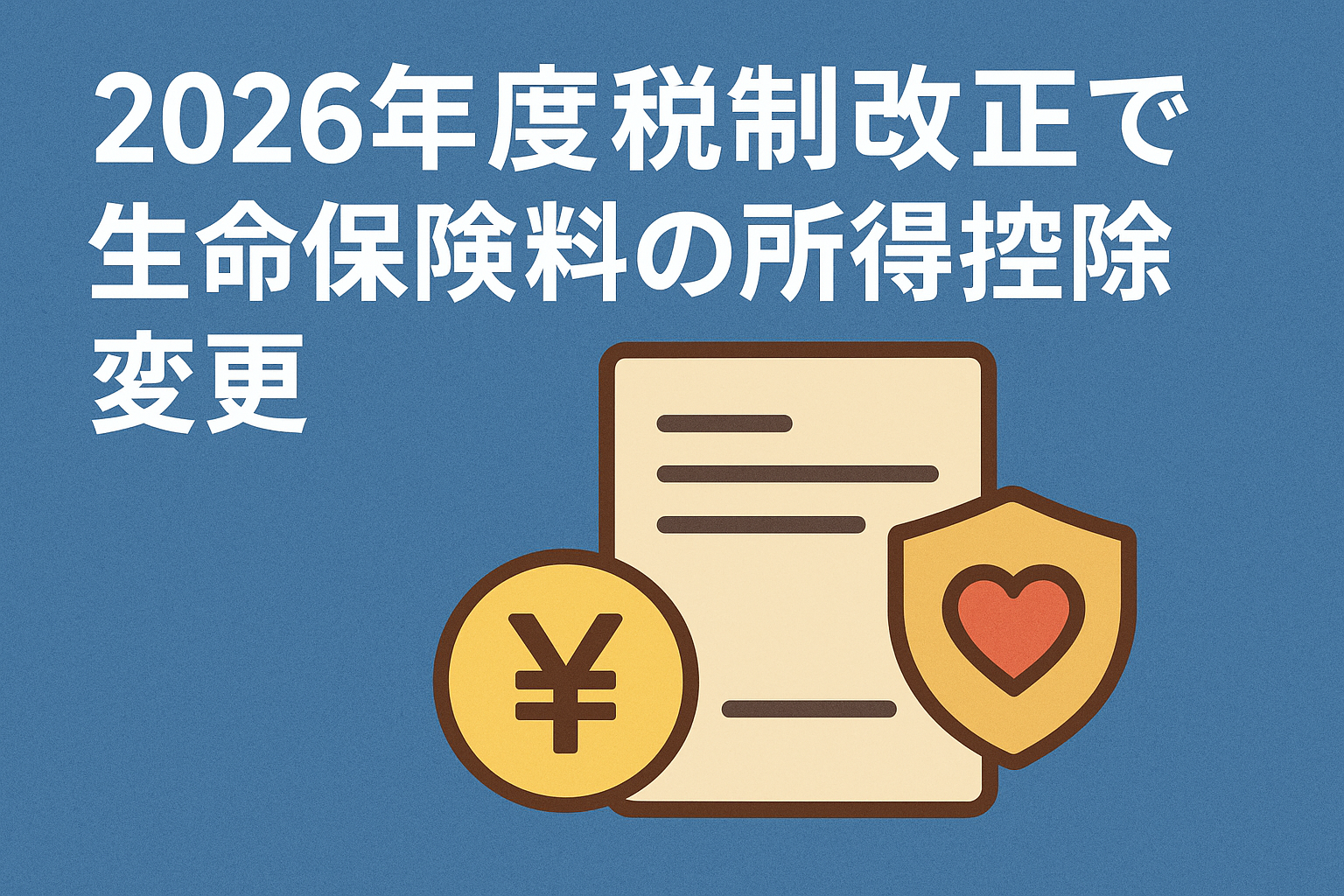子育て支援税制として、23歳未満の扶養親族を有する居住者世帯の生命保険料控除が、4万円から6万円へ限度額が上がることになりました。詳しく見ていきたいと思います。
2026年度税制改正の概要
政府の令和7年度税制改正大綱により、子育て支援税制の一環として「23歳未満の扶養親族を有する居住者」に限り、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算式・上限を引き上げる時限措置が創設されました。この措置は2026年分(令和8年分)の所得税に適用され、一般生命保険料控除の上限が従来の4万円から6万円に引き上げられます。
この制度改正は、子育て世帯の家計リスクに備える遺族保障ニーズへの配慮として設計されており、子育て層向け住宅ローン減税の優遇延長などと並ぶパッケージの一部として位置づけられています。ただし、一般・介護医療・個人年金の合計限度額は従来どおり12万円のまま据え置きとされている点に注意が必要です。
控除額の変化
現行の時限措置(令和8年分・2026年分)の詳細
財務省の令和7年度税制改正大綱では、子育て支援税制の章に現行の時限措置が詳細に明記されています。対象・計算式・上限・適用年が具体的に定められており、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の特別措置として整理されています。
制度比較表
| 項目 | 現行制度 (2025年まで) |
改正後制度 (2026年分から) |
変更点 |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除上限 (23歳未満扶養親族有の場合) |
4万円 | 6万円 | +2万円 |
| 一般生命保険料控除上限 (23歳未満扶養親族無の場合) |
4万円 | 4万円 | 変更なし |
| 対象条件 | 制限なし | 23歳未満扶養親族を有する場合のみ上限拡大 | 条件付き拡大 |
| 合計控除限度額 (一般+介護医療+個人年金) |
12万円 | 12万円 | 据え置き |
| 適用税目 | 所得税・住民税 | 所得税のみ拡大 (住民税は現行通り) |
所得税のみ |
| 制度の性格 | 恒久制度 | 時限措置 (恒久化要望中) |
1年間限定 |
| 決定・適用時期 | - | 2024年12月決定 2026年分所得税から適用 |
2027年申告時 |
控除額計算方法の比較(23歳未満扶養親族有の場合)
| 年間保険料 | 現行制度の控除額 | 改正後の控除額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 25,000円 | 40,000円 | +15,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 50,000円 | +10,000円 |
| 10万円 | 40,000円 | 55,000円 | +15,000円 |
| 12万円以上 | 40,000円 | 60,000円 | +20,000円 |
恒久化に向けた動向
| 時期 | 主体 | 動向 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 政府 | 令和7年度税制改正大綱で時限措置を決定 | ✅ 決定済み |
| 2025年7月 | 生命保険協会 | 恒久化を重点要望として提出 | 📝 要望済み |
| 2025年8月 | 金融庁 | 恒久化を正式要望として提出 | 📝 要望済み |
| 2025年12月(予定) | 与党税制調査会 | 恒久化の可否を決定予定 | ⏳ 審議待ち |
この措置はNHKの年末大綱解説・特集でも「2026年に実施」として整理され、公的メディアでも確認が取れます。また、公的機関系の解説サイトでも「2026年分に子育て世帯の一般枠の限度額が6万円に」と周知されており、制度の認知度向上が図られています。
控除額計算の変更点
新制度では、23歳未満の扶養親族を有する場合の計算方法が変更されます。旧制度(旧生命保険料)のみを支払っている場合は本改正の影響はありませんが、旧生命保険料と今回の対象となる新生命保険料を併せて支払うケースでは、一般生命保険料控除の適用限度額が6万円になります。
重要な点として、今回の上乗せは「所得税」における一般生命保険料枠に限った措置で、住民税側の各枠・合計上限は従前どおりです。所得税では合計12万円、住民税では合計7万円の限度額が維持されています。
制度適用までのフロー
金融庁の2026年度税制改正要望:恒久化の提案
金融庁は8月末に公表した2026年度税制改正要望で、子育て世帯向け生命保険料控除の拡充について、時限ではなく恒久化するよう求めています。要望資料の該当箇所には、令和8年分に講じられた「23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除枠の2万円上乗せ」措置に関する要望事項が整理されています。
この恒久化要望は主要メディア(共同通信系・時事など)でも報じられており、家計の資産形成支援の文脈で注目を集めています。今回の金融庁要望は、NISA拡充(つみたて投資枠の年齢制限見直しや対象商品の拡大)も含むパッケージとして報じられており、総合的な家計支援策として位置づけられています。
「恒久化」の具体像
恒久化の趣旨は、現行の時限措置(対象・計算式・上限6万円)を期限を設けず継続することにあります。一次資料と報道を総合すると、恒久化後も以下が基本線となる見込みです。
- 対象条件:23歳未満の扶養親族を有する居住者(現行時限措置の要件を継続)
- 対象枠:新生命保険料に係る一般生命保険料控除(遺族保障枠)のみ(合計限度12万円は据え置き)
- 控除額:所得税の一般枠上限は6万円(現行4万円→上乗せ2万円)
- 適用開始時期:令和8年分(2026年分)以降について期限なく継続
最終決定は年末の与党税制調査会取りまとめ・法案成立で確定されますが、業界からの強い要望もあり、実現可能性は高いとみられています。
子育て世帯への影響分析
この制度改正により、23歳未満の扶養親族を有する世帯では、年間最大2万円の追加所得控除が受けられます。所得税率が10%の場合、年間2,000円、20%の場合は年間4,000円の税負担軽減効果が見込まれます。
特に影響を受けるのは、子育て世帯で生命保険料を年間8万円以上支払っている家庭です。これまで4万円で頭打ちだった控除額が6万円まで拡大されることで、実質的な保険料負担軽減につながります。さらに、恒久化が実現すれば、長期的な家計計画において安定した節税効果を見込むことができます。
ただし、合計控除限度額は12万円で据え置きとなるため、他の保険料控除(介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)を併用している世帯では、必ずしも満額の恩恵を受けられない場合がある点に注意が必要です。
控除額シミュレーター
あなたの条件で控除額と節税効果を自動計算します。数値を入力すると即座に結果が表示されます。
よくある質問
免責事項
本記事の内容は2025年8月30日時点の情報に基づいており、税制改正の詳細や実施時期は変更される可能性があります。実際の税務申告の際は、税理士や税務署にご相談ください。控除額の計算結果は概算であり、個別の状況により異なる場合があります。